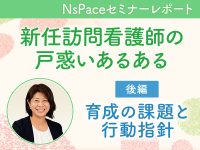IAD(失禁関連皮膚炎)とは? 鑑別が必要な疾患も紹介【多数の症例写真で解説】
在宅療養者によくみられる皮膚症状を、皮膚科専門医の袋 秀平先生(ふくろ皮膚科クリニック 院長)が写真を見比べながら分かりやすく解説。今回はIAD(incontinence associated dermatitis:失禁関連皮膚炎)を取り上げます。 はじめに~普通の皮膚科医が思っていること IADとは何か IAD(アイエーディ)はincontinence associated dermatitisの略で、直訳すれば「失禁関連皮膚炎」となります。2007年、「便や尿が会陰部へ接触した際に生じる皮膚の炎症」として提唱されました1)。日本創傷・オストミー・失禁管理学会の定義2)によれば、IADは「尿または便(あるいは両方)が皮膚に接触することにより生じる皮膚炎」とされており、いわゆる狭義の湿疹・皮膚炎だけでなく、物理・化学的皮膚障害、皮膚障害性真菌感染症を含んでいます。 つまりIADは診断名ではなく、失禁患者における外陰部周辺の広義の皮膚障害を表す概念であって、失禁ケアの重要性、必要性を喚起するためにつくられたものと考えられます。 この連載の第2回で触れましたが、皮膚科の世界では「皮膚炎」は湿疹とほぼ同義語です。一方、真菌による炎症は「真菌感染症」であり、真菌による湿疹(=皮膚炎)とは呼びません。そのあたりが、皮膚科医にとっては「IADの定義がちょっと気持ち悪い」と感じるところになっています。 >>「第2回」についてはこちら湿疹皮膚炎とは? 種類や症状、改善方法が分かる【写真で解説】 IADの重要性 筆者が初めてこのIADという概念に接したときに、正直に申し上げれば「普通に診断すればよいのでは」と思いました。しかし病院、在宅、施設のすべての現場に皮膚科医が居合わせるわけではありません。看護・介護のケアによって予防でき、患者のQOL(quality of life:生活・生命の質)の向上を考えれば、おむつ回りの皮膚のトラブルをIADとして捉えることは十分に意味があると感じています。 私は一般の在宅診療のほか、数件の高齢者施設にも出向いて診療しています。2024年のデータですが、1月から3月までの間に95人の施設入居者の診療を行いました。主訴として一番多かったのは湿疹皮膚炎です。IADをあえて病名としてみると、IADを主訴とする例は6人、主訴ではなく副訴としてIADの状態にあったのは16人。合計すると22名になり、全体の4分の1近くにのぼることが分かりました(表1)。施設でもIADが大きな問題になっていることを感じます。 本稿では皮膚科医として、発生してしまったIADや鑑別すべき疾患などについて解説します。 表1 2024年1~3月における高齢者施設往診時のデータ コラム IADと皮膚科医IADという概念は、皮膚科医の間に広く浸透しているものではないようです。詳しく調べたわけではありませんが、筆者の周囲、特に在宅や施設に関わったことがない医師や、若い皮膚科医の間での認知度が低いように感じました。さらに、IADの延長線上にはMASD(moisture associated skin damage:水分関連皮膚損傷)3)という概念がありますが、そちらに至ってはほとんどの皮膚科医が知らないように思います(筆者も、2024年の第33回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会に参加するまで知りませんでした)。 実際の皮膚の症状を見てみよう ここからはIADとされる状態、あるいはIADと鑑別が必要と思われる皮膚疾患について症例写真をもとに解説します4)。 IADに包括される疾患 (1)(尿・便による)接触皮膚炎刺激性接触皮膚炎で、おそらくこれが頻度としては一番多いでしょう。刺激性接触皮膚炎は皮膚のバリア機能と刺激物との戦いですから、浸軟してバリア機能が落ちている外陰部では容易に発症します(図1)。 図1 刺激性接触皮膚炎 尿・便の刺激や洗いすぎにより紅斑・腫脹・鱗屑がみられます。鱗屑に真菌が存在するかどうかは、視診だけではわからないので検査をおすすめします。 (2)真菌感染症カンジダによる場合と白癬による場合があると思われます(図2)。この連載の第3回で記したように、検査によって真菌を証明することが理想です。 >>「第3回」についてはこちら真菌症とは? フットケアにも活かせる知識【写真で解説】 図2 真菌感染症 (左)臀部の白癬です。本連載の第3回で述べたように、境界明瞭な紅斑・堤防状隆起・中心治癒傾向の3つの特徴を持っています。(右)カンジダ症です。膜様鱗屑を付着しています。視診だけで診断するのは難しいかもしれません。 (3)臀部肉芽種臀部中心に、肉芽腫様の結節が形成される疾患です(図3)。不潔や浸軟が原因とされています。 図3 臀部肉芽腫 肉芽腫様の結節(→)を認める。 (4)間擦疹(かんさつしん)間擦部(鼠径部、肛門周囲など皮膚が擦れて摩擦を受ける場所)に生じる皮膚の炎症です(図4)。 図4 鼠径部に発症した間接疹 * * * 上記(1)(3)(4)は真菌と関係なく発症しますが、それぞれに真菌感染も合併することがあるため注意を要します。 IADと鑑別する必要がある皮膚疾患 (1)単純疱疹と帯状疱疹真菌症と同じく病原体による感染症ですが、単純疱疹と帯状疱疹はIADには包括されていません。この両者は同じヘルペスウイルス科に属するウイルスにより発症し、個疹(一つひとつの皮疹の形)では区別できないため、皮疹の分布や症状などで診断します(図5)。診断が難しい場合、最近では鑑別するためのキットが販売されており、キットを用いた検査も行われています。 図5 単純疱疹と帯状疱疹 個疹(それぞれの皮疹)は頂点が少し陥凹した水疱が基本ですが、帯状疱疹は通常、単一の神経の支配領域に分布するため左右どちらかに限定されます。 (2)腫瘍性疾患図6は前医に湿疹と診断されて外用薬を長く使用されていた例ですが、実際には陰嚢に生じた乳房外パジェット病(アポクリン腺という汗をつくる組織から生じる皮膚がん)でした。湿疹であればIADの範疇に入りますが、腫瘍は尿・便失禁とは関係ないですね。ほかに発生する可能性がある腫瘍として、悪性のものでは基底細胞癌、有棘細胞癌、ボーエン病など、良性では脂漏性角化症や被殻血管腫などが挙げられます。腫瘍か否かを判別するのは意外に難しく、皮膚生検を要する場合もあります。 図6 乳房外パジェット病 基本的にはIADと区別すべきだが、失禁の影響で増悪する場合が多い皮膚疾患 (1)褥瘡褥瘡とIADはもちろん別物ですが、仙骨部から臀部にかけての褥瘡の好発部位はIADが発生する部位に一致し、浸軟や摩擦で皮膚が脆弱化しているため褥瘡もできやすくなっています。実際に診療の場で「これは褥瘡とすべきなのか、IADなのか」と迷う例もあります(図7)。 図7 褥瘡かIADか悩んだ例 「褥瘡ができました」と診察依頼があった例です。丸をつけた仙骨部には瘢痕が見られ、その部分は褥瘡であったように思われます。一方で矢印のびらんは、IADとすべきか、と考えます。 (2)老人性臀部角化性苔癬化皮膚臀裂部の上方両側に、肥厚してザラザラした局面をつくる状態です。「座りダコ」と考えてよいと思います。バリア機能が低下するため、湿疹や真菌症を起こしやすく、乾燥して亀裂を生じ、潰瘍化する場合もあります。保湿や外用薬による治療やケア、姿勢(座り方)の矯正といった介入が必要です(図8)。尿・便の影響を強く受けますが、それらと関係なく発症するためIADに包括はされません。 図8 老人性臀部角化性苔癬化皮膚 老人性臀部角化性苔癬化皮膚です。左右は別の例ですが、角化・苔癬化した皮膚は脆弱で、びらんや潰瘍化しやすくなります。 IADを見たらどうする? IADに遭遇した場合の治療指針として、「おむつ皮膚炎治療アルゴリズム」があります5)(図9)。この場合の「おむつ皮膚炎」はIADと読み替えてよいでしょう。 まずミディアム以下のステロイドを外用し、改善すればそれでOK、改善しない場合に皮膚科医の診察を要請し、必要に応じて真菌検査を行うというものです。結果的に3週間後に6割弱で改善以上という成果を得られていますので、すぐに皮膚科医が診察できない場合は参考にされるとよいでしょう(本当はいろいろな現場で皮膚科医が診察することができればよいのですが)。 図9 おむつ皮膚炎治療アルゴリズム 【おむつ皮膚炎】おむつを当てている部位における紅斑・びらん・浸軟などの皮膚症状常深祐一郎先生の許諾を得て転載 最後に IADについては看護領域で多くの参考となる著作があります。NsPaceの「在宅の褥瘡・スキンケアシリーズ」でも解説されています。今回はIADが生じるメカニズムや、評価のためのIAD-setなどには触れず、純粋に皮膚科医としての視点で述べてみました。みなさまの参考となりましたら幸いです。 >>予防的スキンケアに関する記事はこちら在宅の褥瘡・スキンケアシリーズスキンケアのポイントは?失禁関連皮膚炎(IAD)のアセスメントと予防 執筆:袋 秀平ふくろ皮膚科クリニック 院長東京医科歯科大学医学部卒業。同大学学部内講師を務め、横須賀市立市民病院皮膚科に勤務(皮膚科科長)。1999年4月に「ふくろ皮膚科クリニック」を開院。日本褥瘡学会在宅担当理事・神奈川県皮膚科医会副会長・日本専門医機構認定皮膚科専門医編集:株式会社照林社 【引用文献】1)Gray M,Bliss DZ,Doughty DB,et al.:Incontinence-associated dermatitis:a consensus.J Wound Ostomy Continence Nurs 2007;34(1):45-54.2)日本創傷・オストミー・失禁管理学会編集:IADベストプラクティス.照林社,東京,2019:6.3)Young T:Back to basics: understanding moisture-associated skin damage.Wounds UK 2017;13(2):56-65.4)袋 秀平:IADとする前に―包括される疾患と鑑別が必要な疾患―.MB Derma 2021;316:37-44.5)常深祐一郎,福田亮子,出口亜紀子,他:高齢者のいわゆる「おむつ皮膚炎」に対する治療アルゴリズムの提案.看護研究 2015;48(2):180-188.