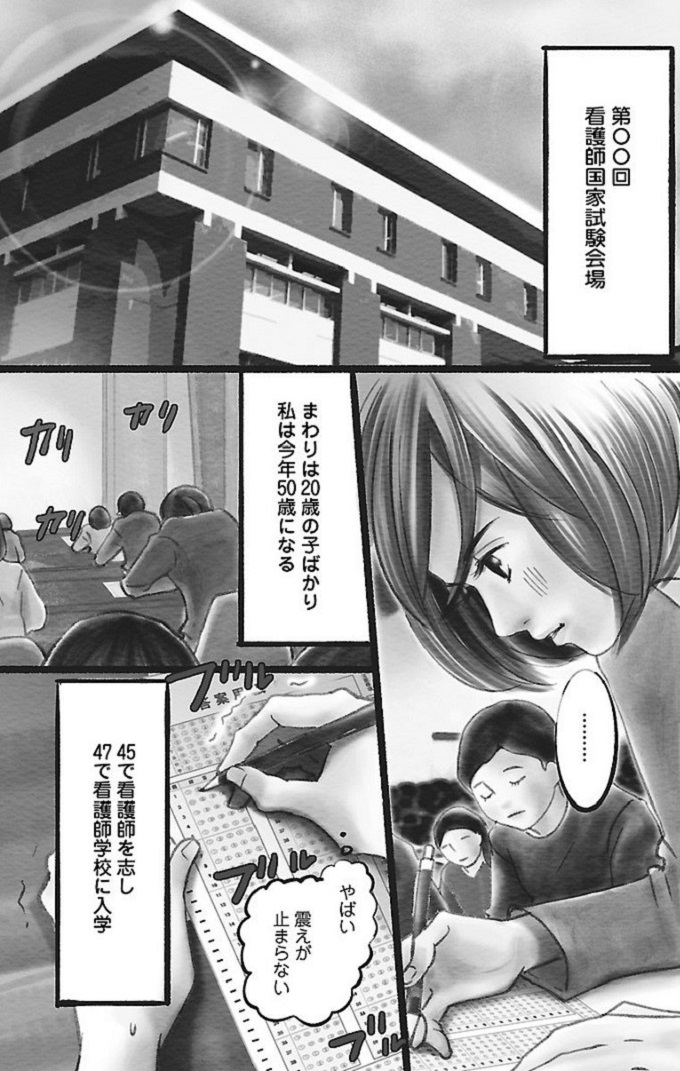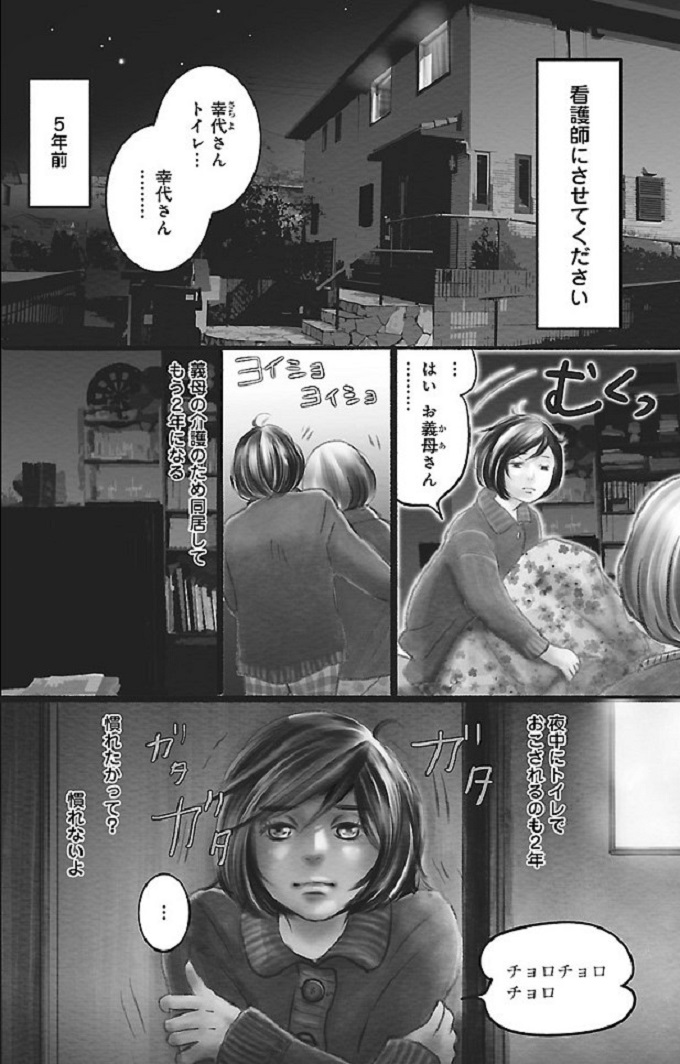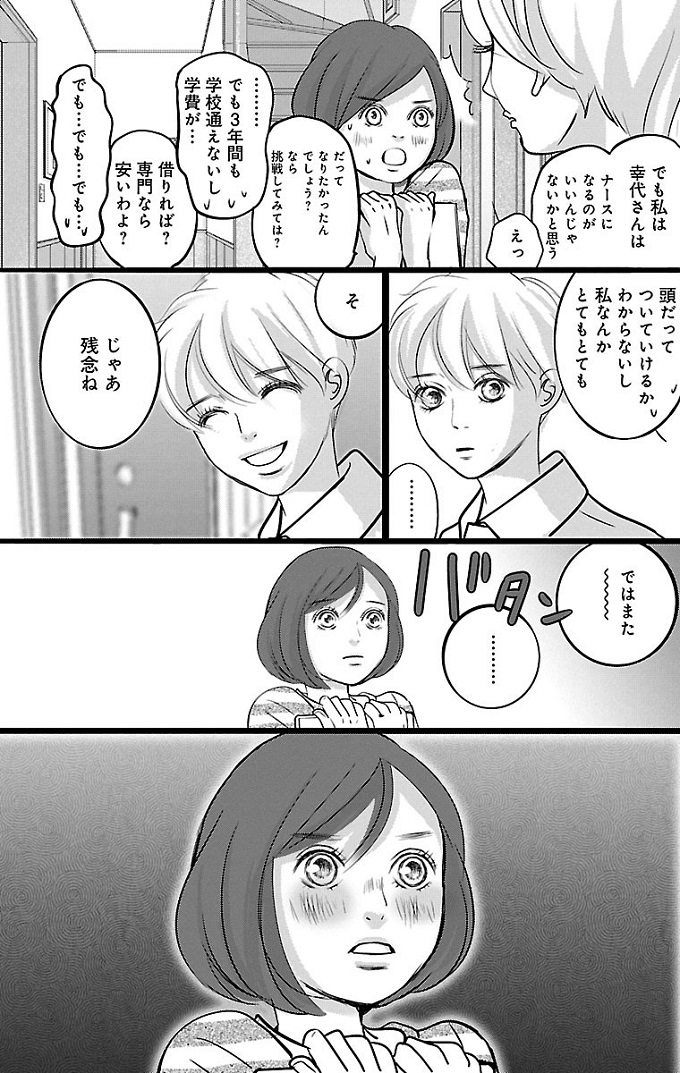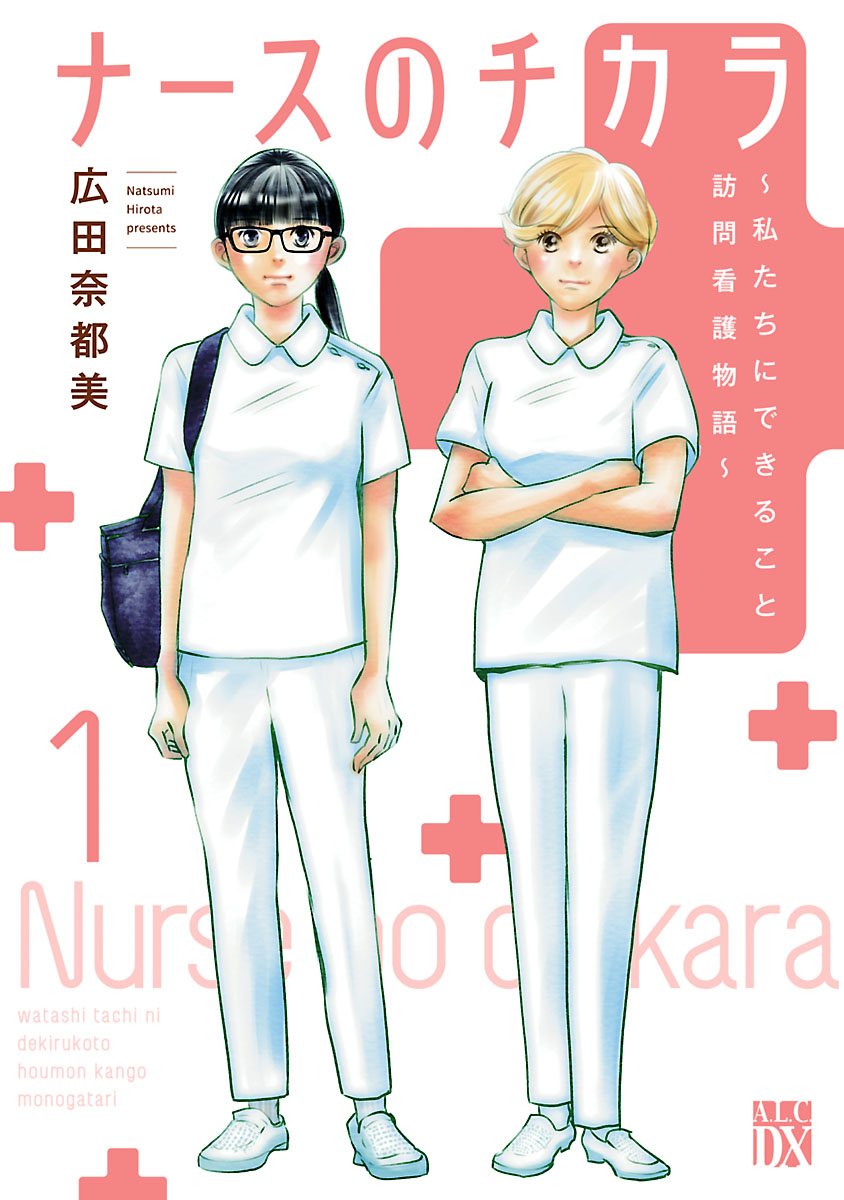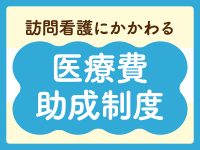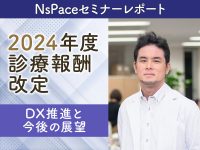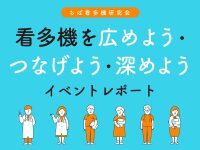渡辺式家族アセスメント 関係性検討と援助の方向性【セミナーレポート後編】
NsPace(ナースペース)のオンラインセミナー「家族看護~渡辺式家族アセスメント/支援モデル 導入編~」(2025年2月21日開催)のテーマは、家族看護に活用したい「渡辺式家族アセスメント/支援モデル」(以下、渡辺式)。開発者の渡辺裕子さんをお招きし、その活用方法を詳しく教えていただきました。セミナーレポート後編では、渡辺式全5ステップのうち3〜5と、検討にあたって意識したいポイントをご紹介します。 ※約90分間のセミナーから、NsPace(ナースペース)がとくに注目してほしいポイントをピックアップしてお伝えします。 >>前編はこちら家族看護 「渡辺式」とは? 場面と登場人物の整理【セミナーレポート前編】>>関連記事「家族看護」シリーズ一覧 【講師】渡辺 裕子さんNPO法人日本家族関係・人間関係サポート協会 理事長/「渡辺式」家族看護研究会 副代表千葉大学大学院 看護研究科を修了後、市町村保健師として勤務。その後「家族看護研究所」「家族ケア研究所」を立ち上げ、2022年から現職。患者とその家族、職場の人間関係に悩む看護職を長年サポートしている。 ステップ3:対象者と援助者の関係性を検討する 対象者と援助者の関係性を検討します。本事例では、以下のような悪循環が生まれていることが見えてきました。 長女と母親長女は母親に対して苛立ちをぶつけ、甘える。しかし、母親に受け流されるため、さらにぶつける。母親は余計にしんどくなってまた受け流す。長女と訪問看護師長女は訪問看護師の前で両親を怒鳴ることで、不満を訴えている。訪問看護師は対処法がわからず、訴えを聞き流す。長女はますます強く訴える。母親と訪問看護師訪問看護師は母親を心配して気遣うが、母親は取り繕い、ますます気になる。 ステップ4:力関係と両者の心の距離感を検討する ステップ4では、ステップ3で整理した関係性をさらに細かく見ていきます。具体的には、「パワーバランス」の検討、相手との間に本来必要なパートナーシップを構築できているかを考えましょう。なお、「本来必要なパートナーシップ」とは、以下の条件を満たすものです。 パートナーシップの条件1. 利用者さんとご家族、援助者が対等である2. お互いの専門性を尊重し、相手に足りないものを交換し合う(訪問看護師は看護の、ご本人やご家族は「利用者さんの人生」の専門家)3. 望ましい心理的距離を保てている4. 目標を常に共有する5. 援助者はできる限りのサポートを提供し、利用者さんやご家族に力を発揮してもらい、協働する 本事例では、長女の訴えのパワーが適正範囲(ベースライン)を超えています。一方の訪問看護師は「あまり関わりたくない」という思いもあり、パワーが低い状態です。 また心理的距離についても、長女はバウンダリー(心の境界線)を超えて訪問看護師のほうに近寄っており、訪問看護師はやや逃げ腰です。 ステップ5:アセスメントをもとに、支援方策を考える ステップ5では、ここまでのアセスメントをもとに、「5つの柱」を意識しながら支援方策を立てます。 援助の方向性5つの柱1. 悪循環を是正する2. パワーバランスや心理的距離の乱れを是正する3. 背景の中で変えられるものにアプローチする4. ストレングスに働きかける5. 課題を共有し、今後の方向性を話し合う 「悪循環の是正」の観点では、聞き流される度に長女の訴えがエスカレートする状況を変えなければなりません。 「パワーバランスや心理的距離の乱れを是正する」という観点では、長女のパワーを下げて訪問看護師のパワーを上げること。つまり適正なバウンダリーを守り、よい距離感をキープすることを目指す必要があるでしょう。 「背景の中で変えられるものにアプローチする」では、ステップ2で整理した背景から、すぐに変えられそうな要素に焦点を当ててアプローチします。ポイントは、チームで取り組むこと。チームで考えれば「声のかけ方がわからない」という悩みは早期に解決できるかもしれません。また、「家族の問題にどこまで関わるべきかわからない」という悩みについても、組織としての判断を検討すると、自身の後ろに支えがあることを実感でき、訪問看護師のパワーの向上につながるはずです。 「ストレングスに働きかける」のは、家族看護において必須。問題ばかりを見ず、どの家族にもある強みに目を向けましょう。 最後の「課題を共有し、今後の方向性を話し合う」では、Aさんの介護をどうしていきたいかを、対象人物みんなで改めて考える必要があります。 具体的な支援方法の案 上記をふまえると、以下のような支援方法が考えられます。 支援方法1長女の背景に焦点を当てて気持ちを想像し、更年期障害の可能性も検討しながら、訴えを受け止める。長女の困りごとを一緒に考える姿勢をもつ。[理由/目的]・悪循環が是正され、心理的距離も少しずつ変化するはず。・長女への理解が深まることで、「援助者を困らせる人」ではなく「困っている人」なのだというリフレーミングが起こる。支援方法2カンファレンスで情報を共有の上、介入の必要性の有無を検討し、チームとして意思決定する。[理由/目的]・訪問看護師のパワーが上がる。支援方法3対象人物の訪問看護師には同行訪問の機会を設け、同僚の対応を見られるようにする。また、長女にかける言葉はチームで検討する。[理由/目的]・訪問看護師の背景に働きかける。支援方法4訪問スケジュールに余裕をもたせる。[理由/目的]・「中途半端な関わりになることへの不安」の解消を目指す。支援方法5長女、母親、訪問看護師で介護の体制について再度話し合う。[理由/目的]・母親にも長女にも過剰な負担がかからない体制をつくる。 このように、分析結果をひとつの仮説として捉え、支援方策を考え実施します。その後、その結果を評価し、さらなるアセスメントを繰り返すことで、支援の質を向上させていきます。 シート作成のポイント 人間関係見える化シート(R)の目的は、完璧に埋めることではなく、支援の糸口を探すことにあります。具体的な支援方法をなかなか見出せない事例もあるかと思いますが、理解が深まるだけでも、援助者の関わり方や対応が変わることもあるでしょう。 なお、このシートは、「誰が悪いか」を決めるものではありません。対象人物の言動の理由や根拠を認め、悪循環を見つけることで、現状を正しく理解しましょう。それができれば、中立性を保持できます。 * * * 渡辺式家族アセスメント/支援モデルは、利用者さん・ご家族への支援を構造的に捉え直す手がかりとなります。家族看護に悩んだ際は、ぜひ渡辺式を使い、現状を俯瞰した上で具体的な方策を考えてみてください。また、人間関係見える化シート(R)を職場内で共有し、共通の視点や枠組み、言葉で語り合える仲間を増やすのも重要なポイントです。本稿が、利用者さんやご家族との関わりにおける課題の整理や問題解決を考える上で少しでもお役に立てれば幸いです。 執筆・編集:YOSCA医療・ヘルスケア