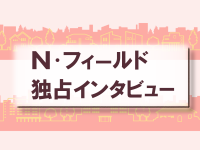どうすればいい? 利用者さんからの拒否

精神科訪問看護に特化して運営しているN・フィールド。今回は、訪問看護のサービス利用に強い拒否感がある利用者への対応などについて、引き続き精神看護専門看護師の中村創さんに話をうかがいました。(以下敬称略)
お話
中村創
株式会社N・フィールド 精神看護専門看護師
サービス受け入れ拒否の背景
[中村]
介護サービスなどでもしばしばみられるように、精神科訪問看護でも、周囲が必要と考えても利用者さんがサービス受け入れを拒否するケースがあります。
具体的な背景には、医療者への不信感が強い、たとえば、特にコロナ禍といった状況では、利用者さん自身が悪いウイルスを持っていると思い込み「来てほしくない」との連絡があるケースや、本人は訪問看護を不要と思っており、理由を尋ねると「『退院をしたければ訪問看護を受けること』と主治医に言われたから」というケースなどがあります。
初回訪問がとても大切
[中村]
「拒否があるから、何もしない」ということはありません。外来受診ができているか、電気メーターはいつもと変わらずに回っているかといった「生存確認」など、最低限からでも、できる支援を模索します。
「自分自身にウイルスがある」と思って「来てほしくない」と言う人は、それだけ不安が強い状態だということです。電話でご様子を確認しながら、訪問できるタイミングを計ります。訪問できたら、少し受け入れるキャパシティが広がってきたのだなと、アセスメント項目として、みさせていただくわけです。
このように、サービス利用に強い拒否感のある利用者さんへの対応においては、初回訪問がとても大切だと思っています。
「来てほしくない」と思われているのに、最初から看護師の専門性を前面に出してしまうと、訪問拒否につながることもあります。心がけているのは、ご本人にとって不快ではない時間を作っていくことです。
役割意識で利用者を『尋問』していないか
[中村]
「安心」「快適」という感覚は、利用者さんの主観によるものです。それをこちらが、「私が来たから安心でしょう」と押しつけてはダメですよね。最初に「私はあなたの敵ではないし、危険な存在でもないですよ」と、いかにして認識してもらうかが、何よりも大切です。
私たちは、気をつけていてもつい、訪問看護師としての専門性を発揮しよう、役割を遂行しようと力が入りすぎて、利用者さんの「安心」や「快適」を引き下げてしまうことがあります。
「薬を飲めていますか」「朝起きられていますか」と言うことは、利用者さんからすると尋問です。そうした医療者視点からのアプローチでは、利用者さんは疲れてしまいます。そうではなく、その人の生活にこちらがいかに乗っていけるか。それが、「安心」「快適」を感じていただける最低ラインの専門性であり、スキルだと考えています。
看護は対人関係のプロセスそのもの
[中村]
そもそも、訪問看護師は利用者に対して「訪問したからには専門職として何かしなくてはいけない」と考えがちではないかと私は考えています。
そうした意識を、実は利用者さんのほうが鋭く感じ取り、プレッシャーを受けていることもあります。
そうならないよう私が心がけているのは、「まず顔見知りになる」です。私は看護理論のなかで「看護は対人関係のプロセス」1)という言葉をとても大切にしています。
見知らぬ看護師である私の訪問を受け入れた利用者さんは、最初、とても緊張しています。それが、氷が溶けるように少しずつ心を開いていってくれる。その感覚を味わうことが、看護師にとっての醍醐味だと思っています。そして、心の氷が溶けるような体験は、利用者さんにとっては、対人関係上のトレーニングでもあるのです。
知的障害や発達障害のある人は、他者とのコミュニケーションに強い苦手意識を持っていることもあります。うまくコミュニケーションをとれなかった体験の累積で、自己肯定感がどんどん低下していることが多いのです。しかし、訪問看護師を受け入れたことで、「あれ? 私、今、人がいても大丈夫だ」と気づく。この体験がとても大切なのです。
何もしないでそっとそばにいる
[中村]
精神科看護には、「ただそばにいること」の意味を示した「シュヴィング的接近」というかかわりかたがあります。これは、何か月も病室で毛布にくるまり、他者とのかかわりを一切持とうとしなかった少女のベッドサイドに、看護師が毎日同じ時刻、静かに30分間座ることで起きた変化を、看護師のシュヴィングが伝えたことに由来します。
数日後、少女は毛布から顔を出して看護師を見ますが、看護師は変わらず静かに座り続けます。それに安心した少女は、起き上がって看護師をじっと見て、翌日には少女のほうから話しかけてきた、というのです。
傷ついてきた人には、まず何も働きかけずに、そっとそばにいる。これが基本ではないかと思うのです。相手に、「そばにいてもいい」と受け入れられはじめる、少しずつ関係ができる。そしてようやく、その人の抱える生きづらさを軽減する方策を考えるお手伝いができるようになります。
専門職にとって「何もしないでそばにいる」というのはとても難しい。しかし、とても大切なことだと思っています。
記事編集:株式会社メディカ出版
【参考】
〇Travelbee,J.『人間対人間の看護』長谷川浩ほか訳.医学書院,1974.