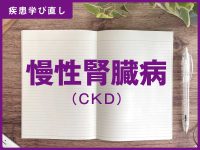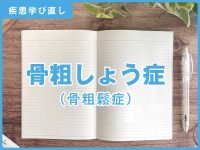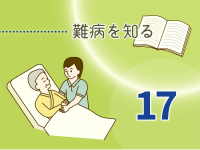結核の感染者数は増えている?症状・原因・感染経路も解説
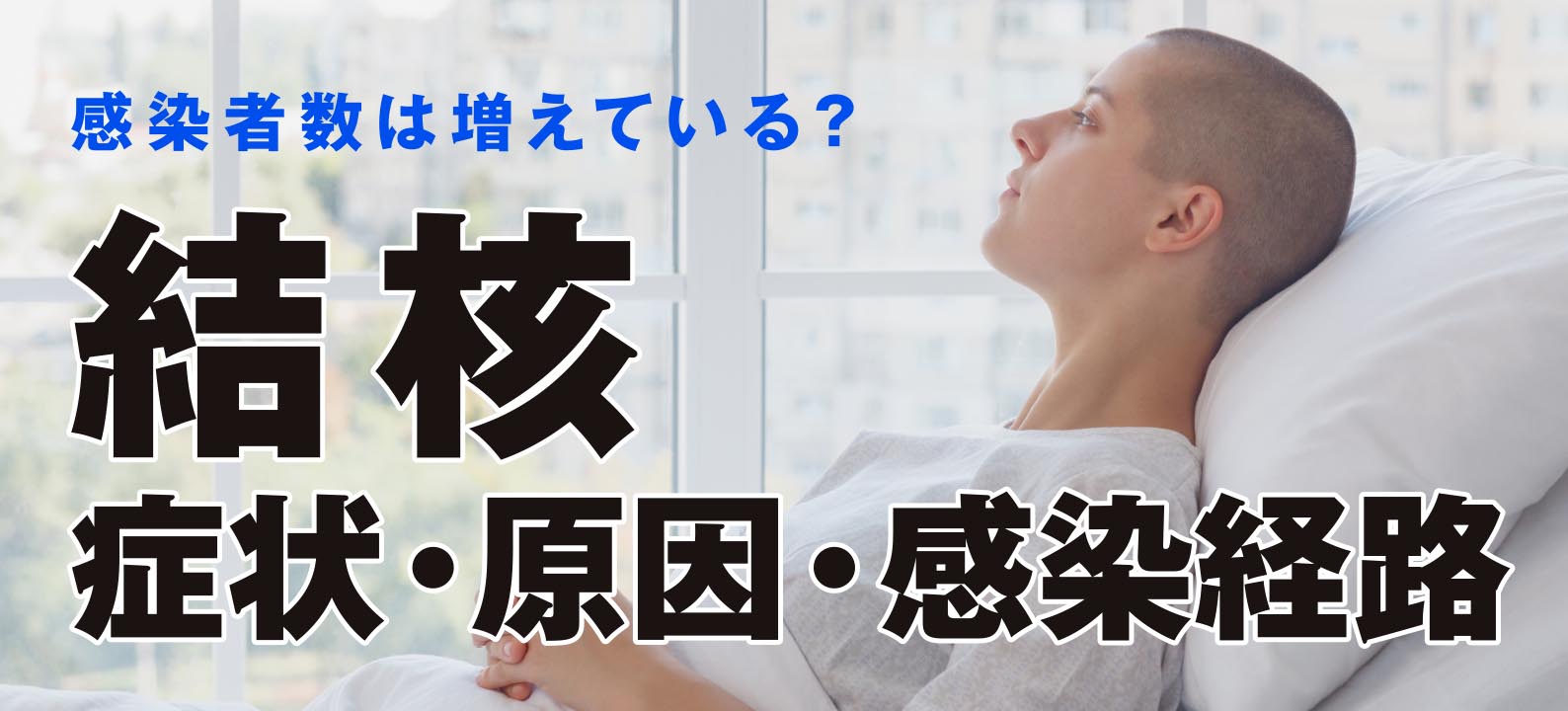
結核は過去の病気と思われがちですが、2025年現在でも世界的に多くの感染者が報告されており、日本でも完全に根絶されたわけではありません。特に高齢者や基礎疾患を持つ人、免疫が低下している人は発症リスクが高く、注意が必要です。
本記事では、結核の最新の感染状況、症状や原因、感染経路、感染を防ぐための対策について解説します。訪問看護の利用者さんやご家族が結核が疑われる症状を訴えた際のアセスメントに役立ててください。
結核とは
結核は、結核菌(Mycobacterium tuberculosis)によって引き起こされる感染症です。主に肺に影響を及ぼしますが、リンパ節や骨、腎臓、脳など全身のさまざまな臓器にも感染する可能性があります。
結核菌は、一般的な細菌とは異なり、手指や土壌、水回りなどの環境中には存在せず、基本的に人の体内でのみ生存し増殖します。感染者が咳やくしゃみをした際に排出される飛沫の中に含まれる結核菌が空気中を漂い、それを長時間かつ大量に吸い込んだ人に感染が広がります。
結核の現在の感染者数
結核の感染状況は近年改善傾向にあり、日本の結核罹患率は低下し続けています。2023年の結核罹患率は人口10万人あたり8.1人で、前年の8.2人からわずかに減少しました。結核の低まん延国の水準である10.0人を下回っており、2021年に初めてこの基準を達成して以来、継続的に低い水準を維持しています。
乳幼児や思春期の若者では発症率が比較的高く、糖尿病、慢性腎不全、エイズ、じん肺などの基礎疾患を持つ人もリスクが高まります。さらに、副腎皮質ホルモン剤やTNFα阻害薬などによる治療を受けている場合、体内の免疫機能が抑制されることで結核の発症リスクが上昇します。
出典:厚生労働省「2023年 結核登録者情報調査年報集計結果について」
結核の症状と進行の特徴
結核は多くの場合、6ヵ月から2年の間に症状が現れます。初期症状は軽く、風邪や慢性的な疲労と勘違いされやすいため、自覚するのが遅れることが少なくありません。
症状は咳や痰、血痰、胸の痛みなどの呼吸器症状だけではなく、発熱や倦怠感、冷や汗、体重減少なども起こります。
特に、2週間以上咳が続く場合は、結核の可能性を考慮し、早めに医療機関を受診することが重要です。結核は感染力が強いため、発症した本人が気づかないまま放置すると、周囲の人々にも感染を広げてしまう恐れがあります。
結核の感染経路
結核の主な感染経路は、飛沫核感染(空気感染)です。感染者が咳やくしゃみをした際に排出される飛沫が乾燥し、小さな粒子(飛沫核)となって空気中を漂います。これを吸い込むことで、健康な人の肺に結核菌が侵入し感染が成立するとされています。
飛沫は5μm以上であり短時間で落下するため、感染は近距離のみに限定されますが、飛沫核感染では5μm以下の粒子が長時間空気中に残るため、感染が広がりやすいとされています。
結核の感染予防には、以下のような消毒液を使った消毒が有効です。
| 高水準消毒薬 | 中水準消毒薬 | 低水準消毒薬 |
| グルタラール フタラール 過酢酸 | 次亜塩素酸ナトリウム アルコール ポビドンヨード | 両性界面活性剤 |
結核の検査
結核の感染を調べる検査は、ツベルクリン反応検査とインターフェロンγ遊離試験(QFT・T-SPOT)です。ツベルクリン反応検査は、BCG接種や類似の非結核性抗酸菌の影響を受けるため単独で結核感染の診断には用いられません。一方、インターフェロンγ遊離試験は結核菌に特異的な免疫反応を検出する血液検査で、結核菌感染の有無を調べるのに有用です。
また、胸部レントゲンや胸部CTにて結核を疑い、喀痰検査などで確定診断を行います。喀痰検査には、結核菌を検出する方法として塗抹検査(顕微鏡検査)、培養検査、核酸増幅検査(PCR法)があります。
- 塗抹検査(顕微鏡検査)
喀痰を染色し、抗酸菌の有無を調べる。ただし、検出された抗酸菌が結核菌とは限らない(非結核性抗酸菌の可能性もある)。 - 培養検査
痰の中に含まれる結核菌を、特殊な培養液で増やして検出する検査。確定診断に有用だが、結果が出るまで数週間かかる。 - 核酸増幅検査(PCR法)
痰の中に含まれる結核菌の遺伝子を検出する検査。結核菌の遺伝子を検出するので、迅速な診断が可能。ただし、菌の生存は確認できないため、培養検査と併用するのが望ましい。また、既往歴に肺結核がある場合、死菌を検出し陽性になる可能性があるため、慎重な判断が必要。
結核のワクチン
結核の予防として広く使用されているBCGワクチンは、結核の感染および重症化を防ぐために開発された生ワクチンです。
接種方法は一般的な注射とは異なり、専用の管針を用いた「スタンプ方式」。ワクチンの液を皮膚に滴下し、針を皮膚に押し当てることで薬剤を浸透させます。
生後1歳までに行うことが推奨されており、特に生後5ヵ月から8ヵ月までの間に接種することが望ましいとされています。
結核疑いのある方への訪問の注意点
結核は空気を介して感染する疾患のため、訪問時には感染対策を徹底することが重要です。感染防護の基本としてN95マスクを適切に装着し、呼吸器を通じた病原体の吸入を防ぐことが求められます。
訪問先の室内環境についても十分な配慮が必要で、窓を開けるなどして定期的に換気を行うことで、空気中の菌濃度を下げるよう努めましょう。
なお、利用者さんの健康状態を把握するためにバイタルサインの測定を行いますが、測定機器や手指の消毒については、ほかの利用者さんと同様の衛生管理を徹底すれば問題ありません。
結核にて在宅療養をする場合の注意点
結核の診断を受けた利用者さんが在宅で療養を行う場合、感染予防の徹底と体調の変化を早期に察知することが重要です。
内服管理については、治療の基本となる抗結核薬を確実に服用し続けることが求められます。薬の飲み忘れや自己判断による服薬中断があると、薬剤耐性結核を引き起こすリスクが高まるため、家族や訪問看護師が服薬状況を定期的に確認し、必要に応じて服薬の支援を行います。
また、在宅療養中の環境整備として、室内の換気を徹底しましょう。結核菌は空気中に長時間浮遊するため、窓を開けて空気の流れを作り、清潔な空間を保つよう心がけます。さらに、同居する家族が感染リスクを減らすためにも、マスクの着用を徹底しましょう。
異常の早期発見も在宅療養の重要なポイントです。結核治療中に発熱や倦怠感が強まる、血痰が増える、体重減少が著しいといった症状が現れた場合、病状の悪化や副作用の可能性が考えられます。こうした変化が見られた際には、すぐに医療機関へ相談し、適切な対応を取ることが必要です。
結核の既往歴がない利用者さんであっても、慢性的な咳や血痰が続く場合は結核の可能性を考慮し、訪問時にはN95マスクを着用しながら対応し、医師へ速やかに報告することが重要です。
* * *
訪問看護師が適切な知識を持ち、早期に異変を察知し対応することで、結核の重症化を防ぐことができます。結核の感染リスクを考慮しながら、適切な対応を心がけましょう。
| 編集・執筆:加藤 良大 監修:村田 朗 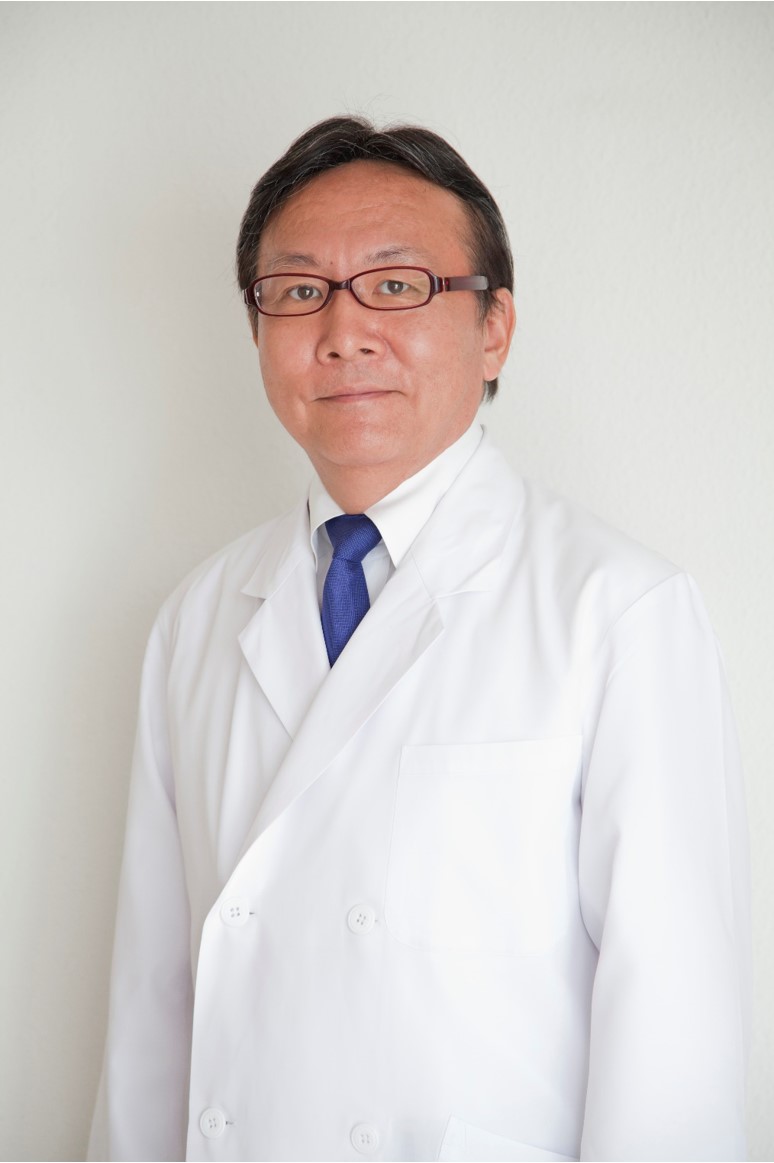 医療法人財団日睡会 理事長 御茶ノ水呼吸ケアクリニック 院長 日本医科大学内科学講座(呼吸器・感染・腫瘍部門)非常勤講師。 日本医科大学、 同大学院卒業。 資格・学会:医学博士、日本内科学会認定内科医、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本睡眠学会会員、肺音(呼吸音)研究会世話人、東京呼吸ケア研究会幹事、American Thoracic Society 会員、European Respiratory Society 会員、International Lung Sounds Association 会員、NPO法人日本呼吸器障害者情報センター顧問、東京都三宅村呼吸器専門診療委託医、日本医師会認定産業医、身体障害者福祉法指定医(呼吸器)、千代田区公害健康被害診療報酬審査委員。 |
【参考】
〇日本小児科学会.「BCGワクチン」(2018年3月)
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_B-06BCG_202312.pdf
2025/6/25閲覧
〇厚生労働省.「2023年 結核登録者情報調査年報集計結果について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001295037.pdf
2025/6/25閲覧
〇厚生労働省.結核「感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-02.html
2025/6/25閲覧
〇東京都感染症情報センター.「結核 Tuberculosis」(2025年2月27日)
https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/tb
2025/6/25閲覧