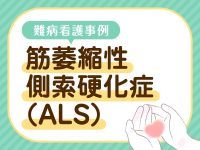エンバーミング(遺体衛生保全)とは? 歴史や目的・意義を解説

エンバーミング(遺体衛生保全)は、故人の姿を生前の安らかな状態に近づけるために、防腐処置や消毒、修復などを施す技術です。ご遺族が心の準備を整え、悲しみと向き合うために重要な手段でもあります。本記事では、日本におけるエンバーミングの先駆者であり、グリーフサポートの普及にも尽力されている橋爪謙一郎氏に、エンバーミングの歴史とその深い意義について詳しく教えていただきます。
目次
知っておきたい、死後の身体変化が与える影響
ヒトが亡くなった後、その身体は適切な処置をしなければ、時間の経過、病気や治療、身体が置かれている環境などの影響を受けて変化し続けます。変化を最小限にして、その人らしい姿を保てるかどうかは、家族のグリーフに影響を与える要素となることから、身体の状態に合わせた適切な処置が求められます。
看護師の皆さんは、故人の尊厳を守るために、ていねいにエンゼルケアを行っていることと思います。また、遺されたご家族が、故人のつらそうな表情を目の当たりにすることで、罪悪感や苦しい感情を持たないように配慮されていると思います。エンバーミングについて理解をしていただくために、まずは亡くなった後の身体の変化、「死体現象」についてお話しすることから始めたいと思います。
ヒトが亡くなった後の変化:死体現象とは
皆さんは「死体現象」という言葉を聞いたことはあるでしょうか? この現象は、早期と晩期に分けられます。
晩期死体現象には腐敗や自家融解が含まれているため、この現象を止めるためにドライアイスや保冷庫などを用いて処置することで対応します。しかし、早期死体現象に対しては、必要な対処がされていないことが多くあります。
早期死体現象には、以下が含まれます。
| ・血液の変化 ・死斑の発現 ・死後硬直 ・死体温の変化 ・乾燥 ・角膜の乾燥と混濁など |
腐敗の進行は抑えられたとしても、それよりも早い時期に始まっている変化は、残念ながらそのまま進むことがあります。そうなると、看護師の方々がエンゼルケアをしっかり行ったとしても、時間の経過とともに変化が起こってしまうのです。
もう少し分かりやすく具体的にお伝えしましょう。血管中に残った血液は、重力に従って上から下へと移動していきます。身体が仰向けに寝かされている状態であれば、背中側の部位に血液による変色が強く現れ、それと同時に、顔や腹部の表皮で乾燥が進みます。
心停止とともに血流が止まり、体内からの水分補給が途絶えている上に、重力の働きによって、顔の表皮の乾燥がさらに進んでいきます。そのため、きれいに施された化粧であっても、崩れたように見えることがあるのです。特に粘膜部分は乾燥しやすく、唇やまぶたに大きな変化がみられます。本来は保湿が必要ですが、それが行われないと、乾燥が進み、口元やまぶたが開いてきてしまいます。
エンバーミングの歴史と日本での普及
エンバーミングは、日本語で「遺体衛生保全」と訳されます。歴史をたどると、古代エジプト時代のミイラづくりが起源とされています。時代が進むにつれてヨーロッパに伝わり、医学の進歩のために解剖用の遺体を保存する目的でさらに発展しました。その後、アメリカにも伝わり、1900年代には教育制度やライセンス制度が確立され、医学の進歩とともに薬品の開発や技術革新が進み、現代に至ります。
日本では、1988年に埼玉県で一般の方向けに初めてエンバーミングが提供されました1)。その後、全国に広がり、2025年現在では32の都道府県で、91の施設においてエンバーミング処置が提供されています(日本遺体衛生保全協会調べによる)。
このようにエンバーミングは、長い歴史と技術の積み重ねを経て、現代においても重要な役割を果たすようになりました。
エンバーミングの目的と意義
エンバーミングには「防腐」「消毒」「修復・化粧」という3つの目的があるといわれています。
| 防腐:体内のタンパク質が腐敗・自家融解することをホルムアルデヒドやアルコールなどの薬品を注入浸透させることによって抑制する。 消毒:薬品を注入し浸透させ、あるいは表皮に塗布することによりウイルスや細菌を不活性化する。 修復・化粧:病気療養中および死後変化によって変化したお姿を生前の安らかだった頃の姿、表情に近づける。 |
しかし、これだけを聞いても、実際に利用する方にとってどのようなメリットがあるのか分かりにくい部分があると思います。エンバーミングをすると、ご遺族にとってどのような意義や価値があるのかについて解説していきます。
時間の制約から解放される
エンバーミングをすることによって、慌てて葬儀をする必要がなくなります。ご遺体の変化が進むことを考えて、できるだけ早く葬儀を行った結果、「気持ちの整理もつかないままお別れをしなければならなかった」と後悔するご家族は少なくありません。また、変化を抑えるために、専用の保冷庫に預けることをすすめられ、故人と会えないまま葬儀当日を迎えることもあります。そうしたケースでは、「亡くなった」という実感がないまま「気がついたら葬儀が終わっていた」と感じる方もいらっしゃいます。
一方で、エンバーミングを施したことによって、体調を崩されたご家族の回復を待ち、家族全員が揃ってから葬儀を行うことができたケースもあります。このように、最後のお別れを一緒に過ごしたい人たちのスケジュールを尊重した上で、葬儀の日程を決めることが可能になるのです。
過度に冷やす必要がなくなる
葬祭業の立場からすれば、ドライアイスや保冷庫などを使用してご遺体の温度を下げ、腐敗の進行を遅らせることは当たり前の対応です。しかし、その身体の冷たさにショックを受けるご家族は多く、「こんなに冷たくなって……」というお声をよく聞きます。
エンバーミングを施した場合は、ほとんどのケースでドライアイスを使用する必要がなくなります。エンバーミングを施した故人に触れたご家族から、「冷たくないんですね。以前に葬儀をした時は、身体に霜がつくほど冷やされてしまって、本当にかわいそうに思いました」とお話しいただいたことがあります。実は違和感を持っていても「仕方ない」と感じるご家族が多いのだと思います。
もちろん、我々エンバーマーが処置をする前に日数が経過し、腐敗が進行してしまった場合には、エンバーミングを行っただけでは変化を止めることができないケースもあります。そのため、死亡後はできるだけ早めに処置することが望ましいのです。
その人らしさを取り戻す
エンバーミングを施すことによって、病気や治療などの影響でやつれてしまっているお顔やお姿を安らかだった頃に近づけることが可能です。生前にどのような病気を患い、どのような治療を受けていたのかといった情報を、エンバーマーが詳細に渡って把握できれば、ご遺体の状態を改善することができるようになります。
ご遺族からの依頼の多くは、「できる限り元気だった頃の姿や表情を取り戻してほしい」というものです。エンバーミングによって防腐され、安定した状態であれば、傷の修復や含み綿などでは改善が難しい「痩せた部位」の修復も可能になります。
また、ドライアイスや保冷庫による処置では、必要な追加処置を行わなければ、乾燥が進み、口やまぶたが開いたり、変色が進んだりすることがあります。エンバーミングを施すことによって、体内から保湿されるため、過度の乾燥を抑えることができます。
さらに、表皮からも保湿することで、肌が整った状態で化粧を行うことが可能になり、その人らしさを取り戻すことにもつながります。使用する薬品に含まれる色素が組織に浸透することで、血色の悪かった部分にも自然な色味が戻るため、厚く化粧をする必要がなくなるケースもあります。
* * *
このように、エンバーミングは、ご遺族が「死」を緩やかに受け入れ、大切な人と向き合いながら最後のお別れの時間を過ごすために、役立つ手段の一つだといえるのです。
| 執筆:橋爪 謙一郎 株式会社ジーエスアイ 代表取締役 一般社団法人グリーフサポート研究所 代表理事  米国で葬祭科学とエンバーミング、グリーフサポートを学び、帰国後(有)ジーエスアイと(一社)研究所を設立。現在は東大大学院で脳科学的視点からグリーフの研究を行う。 編集:株式会社照林社 |
【引用文献】
1)日本遺体衛生保全協会:エンバーミングとは- 医療従事者の立場から.
https://www.embalming.jp/embalming/medic/
2025/6/20閲覧