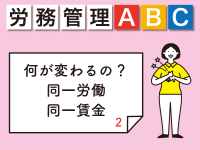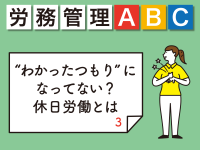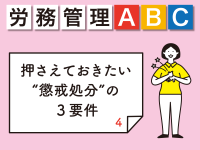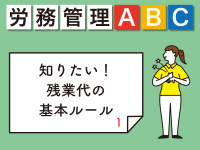第5回 賃金・退職・懲戒・解雇編/[その1]固定残業代、正しく理解・運用できていますか?
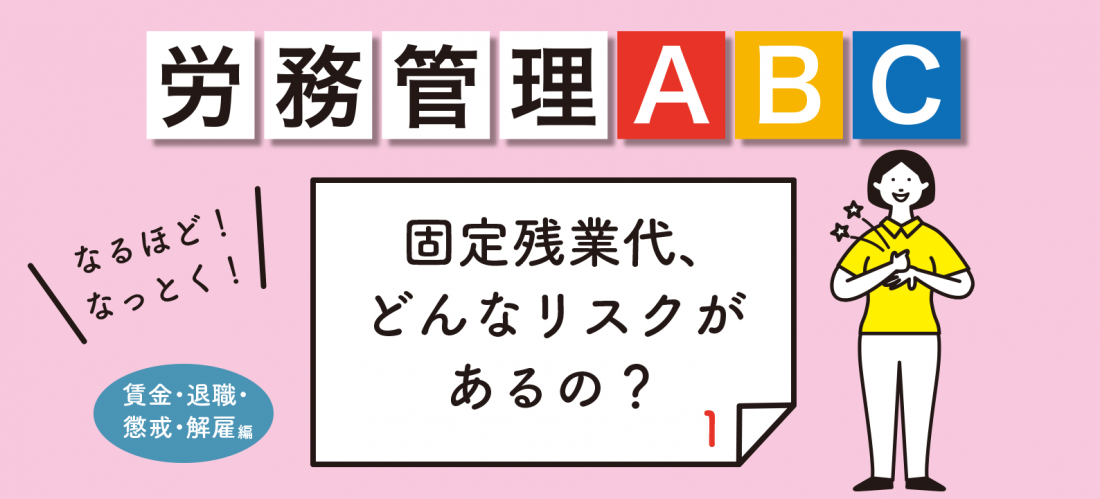
「固定残業代」は、適切に運用ができていないと事業者としてとても大きなリスクを負うことになりますが、正しく運用できていない事業所は少なくありません。ある日突然、元従業員から数百万円や、場合によっては1000万円を超える請求がくることもあります。法的に正しい知識を理解して、就業規則や運用の見直しを進めましょう。
 私の事業所は残業が多いので、従業員に対して、基本給30万円に加えて、固定残業代として毎月5万円を支給しています。固定残業代を毎月払っているのですから、いくら残業させても問題ないし、残業代の計算はしなくても大丈夫ですよね?  いいえ、残業時間は管理しなければなりませんし、固定残業代を超えた分の残業代は必ず支払わなければなりません。 |
固定残業代とは
「固定残業代」(「みなし残業代」や「定額残業代」とも呼ばれます。)とは、時間外労働や休日労働や深夜労働に対して支払われる割増賃金(これを俗に「残業代」と呼びます。)を、あらかじめ、一定額支払っておく制度のことをいいます。
この「固定残業代」は、ご質問のように、「固定残業代を毎月払っているのだから、いくら残業させても問題ないし、残業代の計算はしなくても大丈夫」と誤解されていることが多くあります。例えていうならば、固定残業代を、携帯電話の「ネット無制限使い放題」のようにとらえているわけです。
しかし、そのような完全な固定残業代制度というものは、労働基準法37条に違反するため許されません。
固定残業代とは、携帯電話で例えるならば、「ネット5ギガ使い放題」のようなものです。5ギガまではネット回線の利用料金は別途かからないわけですが、5ギガを超えて使う場合は、別途利用料金を支払わなくてはならないわけです。
固定残業代の考え方もこれと同じで、例えばご質問のケースのように5万円の固定残業代を毎月支払っているならば、残業代は5万円までは支払わなくてもよいですが、5万円を超える残業をさせた場合は差額を支払わなくてはいけません。ある月に7万円分の残業をさせたならば、2万円の差額を別途支払う必要があるということです。
そのため、いかに固定残業代を支払っていたとしても、月々の労働時間・残業時間はしっかりと把握しておく必要があります。そうしないと、一体いくらの差額が発生しているのか把握できず、差額を支払うことができないためです。
  固定残業代制においても月々の労働時間・残業時間の管理は必要です。固定残業代を超えた差額分の残業代は必ず支払いましょう。 |
 私の事業所では、事業所の事務長に対して、基本給として30万円を支払い、職務手当として10万円を支払っています。職務手当は、事務長という重要なポジションについていることに対する役職手当としての意味と、固定残業代としての意味があります。ただし、職務手当10万円のうち、いくらが役職手当で、いくらが固定残業代なのかは明確にしていません。この場合、10万円分の固定残業代を毎月支払っているのですから、それを超える残業代の差額のみを支払えばよいのですよね?  いいえ。この場合、固定残業代という制度自体が無効になる可能性があります。 |
固定残業代が有効になるための要件
これまでに述べたとおり、固定残業代は、その額の分を超えて残業をさせた場合は、必ず差額を支払わなければなりません。
ここから、固定残業代が有効といえるための要件が導き出されます。すなわち、①固定残業代が、時間外労働などの割増賃金の「対価」として支払われていること(対価性の要件)、②その割増賃金部分が、他の賃金と判別することができること(判別可能性の要件)です。
少しわかりにくいと思いますので、具体的に見ていきましょう。
①について。ご質問のケースでは「職務手当」という名称がついていますが、これだと「固定残業代」とは別の名称であるため、一見して、それが割増賃金の代わりに支払われているということがわかりません。そういった場合、事業所が、「この職務手当は、固定残業代として支払っているのですよ」と主張しても、裁判所に信用してもらえないことがあります。手当の名称ですべてが決まるわけではありませんが、少なくとも給与規程や雇用契約書において「その手当を割増賃金の対価として支払っていること」を明記しておくべきです。
次に②について。ご質問のケースを例にとれば、「職務手当」として10万円を支払っており、その中には、役職手当としての意味と、固定残業代としての意味が両方含まれているということです。この時、例えば「役職手当4万円、固定残業代6万円」のように、固定残業代の金額を、他の賃金から区別することができるのであれば、労働者としては、「固定残業代6万円を超えて残業したら、別途差額を支払ってもらえるんだな」と理解できるわけです。
しかし、ご質問のケースのようにその内訳が不明確な場合は、労働者の立場からすると、「固定残業代は10万円のうち一体いくらで、自分はどれだけ働いたら固定残業代を超える分の差額を支払ってもらえるのか」という点がわかりません。
もしも無効とされた場合は・・・・・・
そうすると、固定残業代制は無効とされるリスクが出てきます。無効となった場合は、割増賃金を算定する際の基礎賃金が40万円(30万円+10万円)に跳ね上がり、さらに、固定残業代はこれまで一切支払っていなかったことになるわけですから過去にさかのぼって割増賃金を払い直すことになるという「ダブルパンチ」をくらうことになります。
その結果、固定残業代が無効と判断された場合は、通常の残業代の未払い案件よりも支払うことになる残業代の額が高額になりがちです(1000万円を超えることもあります)。
現場の対応
そのため、(1)就業規則(給与規程)において固定残業代が割増賃金の対価として支払われるものであることを明記し、(2)個別の雇用契約書において、固定残業代の額と、そこに含まれる時間外労働などの時間数を明記し、(3)さらに、給与明細において、「固定残業代」といった費目を設けて他の賃金と明確に区別して給与を支給し、(4)固定残業代分を超える残業をしてもらった場合には、毎月差額を支払っておく必要があります。なお、(2)について、少なくとも、固定残業代に含まれる時間外労働の時間数は、36協定の延長限度時間である45時間を超えないようにしておくべきでしょう。
 固定残業代が有効といえるためには2つの要件が必要です。 ①固定残業代が、時間外労働などの割増賃金の「対価」として支払われていること(対価性の要件) ②その割増賃金部分が、他の賃金と判別することができること(判別可能性の要件) |
**
前田 哲兵
弁護士(前田・鵜之沢法律事務所)
●プロフィール
医療・介護分野の案件を多く手掛け、『業種別ビジネス契約書作成マニュアル』(共著)で、医療・ヘルスケア・介護分野を担当。現在、認定看護師教育課程(医療倫理)・認定看護管理者教育課程(人事労務管理)講師、朝日新聞「論座」執筆担当、板橋区いじめ問題専門委員会委員、登録政治資金監査人、日本プロ野球選手会公認選手代理人などを務める。
所属する法律事務所のホームページはこちら
https://mulaw.jp/
記事編集:株式会社照林社