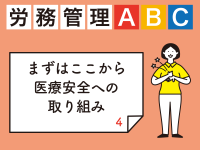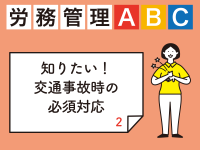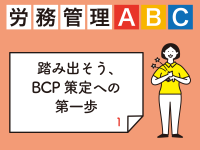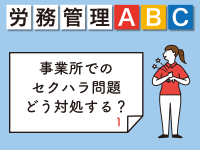第7回 防災対策、交通事故、個人情報保護、医療事故編/[その3]改めて考えたい、利用者様の大事な個人情報の取り扱い方
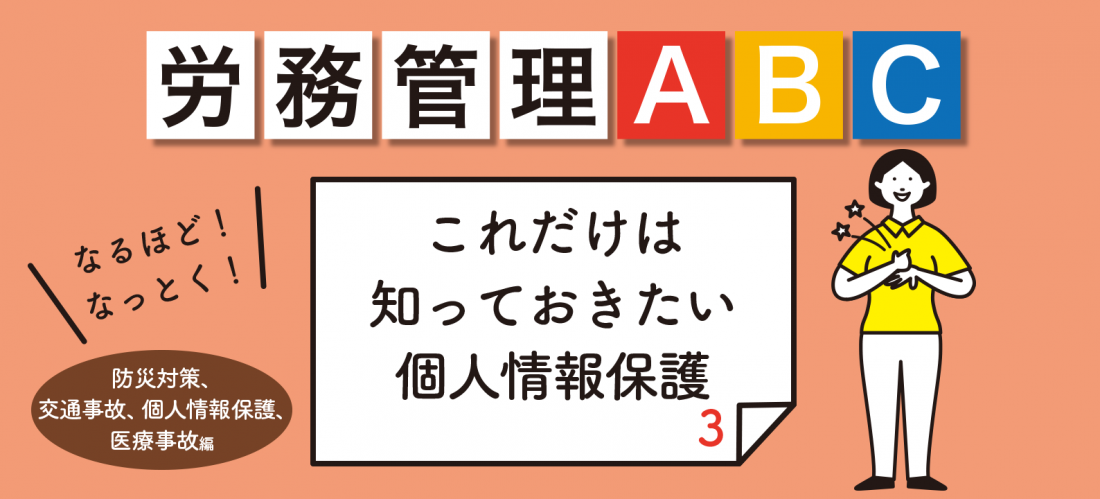
昨今、個人情報に対する社会の意識は日増しに高まるばかりです。個人情報保護の重要性を理解しておくことは、事業所を営んでいくにあたって必須といえます。今回は、個人情報保護の基本的な考え方を解説したいと思います。
 突然ですが、クイズです。以下に掲げる職業の共通点は何でしょう? ・医師、歯科医師、助産師、看護師 ・弁護士、弁理士、公証人 ・宗教家 |
看護師に与えられた特権
医療者・法律家・宗教家というあまり見ることのない組み合わせですね。答えがわからないという方も多いのではないでしょうか。
実はこれらは、刑事訴訟法149条によって、刑事裁判において「証言拒絶権」という特権を与えられている職業です。看護師であれば、裁判所から刑事事件について証言するように言われても「患者さんから聞いた秘密は証言しません」と言えるわけです。このような特権は、上記の職業以外には与えられていません。すべての国民は、裁判所から証言を求められたら証言する義務を負っているわけですから、看護師の皆様は、とても強力な特権を法律で与えられているわけです。
ではなぜ、そのような特権が与えられているのでしょうか?
それは、上記の職業はいずれも「人から重大な秘密を聞くことを前提に仕事をしている」ためです。適切なケアを提供するためには、患者から、病歴だけでなく生活状況などさまざまなことを聞く必要があるでしょう。ただ、患者側からすると、話した内容(秘密)を看護師が守ってくれないと、すべてをありのまま話すことができません。
そこで、法律は、看護師に対して証言拒絶権を与え、患者が看護師に対して安心して秘密を話せるようにしたというわけです。
厚生労働省が定めるガイダンス
国は、医療・介護現場の個人情報保護について、詳細なガイダンスを定めています。具体的な事例集も付いていて、管理者にとっては参考になる情報が詰まっています。
『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス』
『「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)』
守るべき「個人情報」とは
個人情報保護法における「個人情報」とは、要するに「個人を識別することができる情報」のことをいいます。
ポイントは、ここでいう「情報」には、文字情報だけでなく、顔写真・音声・映像なども含むということです。
また、「他の情報と照合することよって特定の個人を識別することができる情報」も個人情報に含まれます。とすれば、ステーションが利用者様から得る情報は、およそすべてが個人情報に該当すると言っても過言ではありません。例えば上記ガイダンス(6〜7頁)では、以下の情報が個人情報にあたるとされています。
| ○医療機関等における個人情報の例 診療録、処方せん、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、調剤録 など ○介護関係事業者における個人情報の例 ケアプラン、介護サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容等の記録、事故の状況等の記録 など |
「要配慮個人情報」とは
さらに、①身体障害、知的障害、精神障害に関すること、②健康診断の内容、③診療や調剤の内容といった医療に関する情報は、単なる個人情報ではなく、「要配慮個人情報」と呼ばれ、特に厳重な取り扱いが求められています(個人情報保護法施行令第2条)。
これらの情報は、不当な差別・偏見の原因となり得るため、犯罪歴情報などと並んで、特に保護すべきと考えられているためです。
このように、普段から皆様が扱っている診療情報というのは、実は、きわめてプライバシーの度合いが高い情報であるということを自覚するようにしましょう。
 ・個人情報とは「個人を識別することができる情報」をいい、「他の情報と照合することによって特定の個人を識別することができる情報」も含まれます。 ・①身体障害、知的障害、精神障害に関すること、②健康診断の内容、③診療や調剤の内容といった医療に関する情報は、「要配慮個人情報」と呼ばれ、特に厳重な取り扱いが求められています。 |
 先日、利用者様の息子だという方からステーションにお電話がありました。「20年近く父(利用者様)と絶縁していたけど、相続のこともあるし、様子が気になった。現在の病状はどうなっているか教えてほしい」とのことでした。息子さんですから、父親の病状を教えても問題ないですよね?  いいえ。個人情報(病状)の第三者提供にあたりますので、利用者様の同意を得る必要があります。 |
個人情報を第三者に教えてもよい場合とは?
個人情報の取り扱いの中で最も重要なテーマが、「どのような場合に外部に情報を提供してよいか」という問題です。これを「第三者提供」と呼びます。
これは個人情報保護法第23条において定められているのですが、ポイントは「原則として本人の同意を得ることが必要だ」ということです。
例外的に本人の同意を得なくてもよい場合というのは、①高齢者虐待が疑われる場合に通報するような場合や(これは高齢者虐待防止法で許容されています)、②本人の生命・身体・財産を守るために緊急を要する場合くらいです。
そのほか、「黙示の同意」というロジックもよく使われます。これは、「本人に聞いたら、まず間違いなく同意するだろうと考えられる場合」をいいます。例えば、同居している家族に病状を説明するような場合は、本人は同意すると考えられるため、わざわざ本人に「ご家族にお話していいですか?」と尋ねて同意を得なくてもよいとする考え方です。
しかし、ご質問のケースでは、20年近く絶縁していたということですので、利用者様が同意するかどうかはわかりません。原則に立ち返って、利用者様からきちんと同意を得る必要があります。
医療情報の特殊性を理解する
ステーションの管理者としては、「普段、医療現場が扱っている情報というのは、実は法律上はトップレベルのプライバシー情報なんだ」ということを認識していただくことが何よりも重要です。スタッフに対して研修会を実施するなど、ステーション全体で情報管理に対する意識を高めるようにしましょう。
 ・医療現場で取り扱う情報は、法律上はトップレベルのプライバシー情報だという認識をもつことが何よりも重要です。 ・個人情報を外部に提供する場合(第三者提供)は、原則として本人の同意を得ることが必要です。 |
| 前田 哲兵 弁護士(前田・鵜之沢法律事務所) ●プロフィール 医療・介護分野の案件を多く手掛け、『業種別ビジネス契約書作成マニュアル』(共著)で、医療・ヘルスケア・介護分野を担当。現在、認定看護師教育課程(医療倫理)・認定看護管理者教育課程(人事労務管理)講師、朝日新聞「論座」執筆担当、板橋区いじめ問題専門委員会委員、登録政治資金監査人、日本プロ野球選手会公認選手代理人などを務める。 所属する法律事務所のホームページはこちら https://mulaw.jp/ 記事編集:株式会社照林社 |